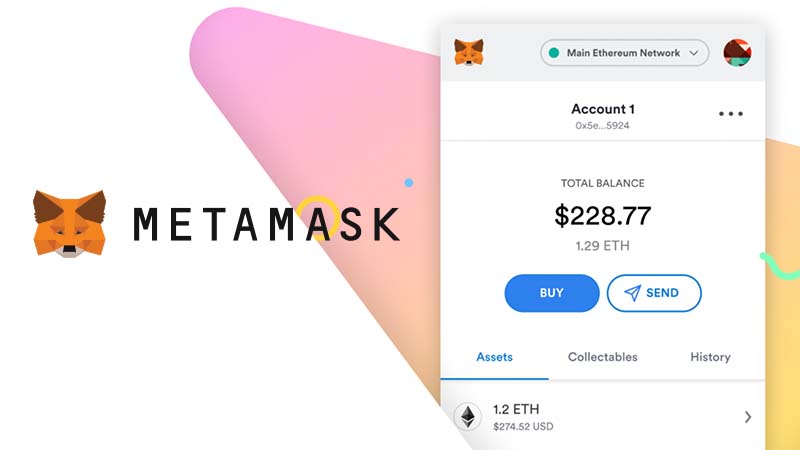国内初の日本円連動型ステーブルコイン「JPYC(ジェイピーワイシー)」が注目を集めています。
金融庁の制度整備を背景に誕生し、2025年8月に資金移動業者として正式に認可を受けたことで、安心して使えるステーブルコインとして大きな信頼を獲得しました。銀行振込よりも低コストで高速な送金、NFT購入やWeb3サービスでの決済、さらには企業間取引や国際送金にも広がる可能性を秘めています。
この記事では、JPYCの仕組みや特徴、購入方法、実際の活用シーン、そして将来性までを徹底解説します。
JPYC(ジェイピーワイシー)とは?
JPYCとは、日本円に1対1で連動する国内初のステーブルコインです。価格安定性を持ち、日本円と等価で利用できるデジタル通貨として注目を集めています。
金融庁の制度整備を背景に誕生し、安心して使える暗号資産の新しい形を示しています。
国内初日本円に連動したステーブルコイン「JPYC」
JPYC(ジェイピーワイシー)は、日本円と連動する国内初のステーブルコインです。JPYCは、1 JPYC=1円の価値を持つよう設計されたブロックチェーン上のデジタル通貨であり、常に日本円と同等の価格安定性を維持することを目指しています。
JPYCを利用することで、ブロックチェーン上で24時間365日いつでも即時に価値をやり取りでき、従来の銀行送金と比較して手数料も大幅に削減できます。
また、NFT購入やWeb3サービスでの決済など、価格変動の大きいビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)では難しかった用途でも、常に1円と等価であるJPYCなら安心して利用できる点も魅力です。
日本発のデジタル円として、JPYCは今後のデジタル経済基盤の一角を担う存在として期待されています。
JPYCの開発企業と歴史
JPYCを開発・発行するのはJPYC株式会社というスタートアップ企業です。同社は2019年11月に岡部典孝(おかべ のりたか)氏によって創業されました。
岡部氏はブロックチェーン推進協会の理事やDeFi協会ステーブルコイン部会長なども務める、日本のブロックチェーン業界をリードする実業家です。JPYC社は2021年より本格的に日本円ステーブルコイン事業を展開し、2021年に最初のJPYCトークンを発行しました。
JPYCの歴史を振り返ると、2021年1月にJPYC(現JPYC Prepaid)の発行開始、その後ユーザー数と流通量を着実に拡大してきました。法規制面では、当初ステーブルコインに関する明確な法律がなかったため、JPYCは前払式支払手段(プリペイド型)として発行されました。
2023年に資金決済法が改正されステーブルコイン発行の制度が整うと、JPYC社は新たな枠組みでのステーブルコイン発行に動き出します。
2023年11月には三菱UFJ信託銀行が提供するProgmat基盤を通じた信託型ステーブルコイン発行(JPYC Trust)計画を発表し、そして2025年8月には金融庁から資金移動業者のライセンス登録を正式に受け、日本初の円建てステーブルコイン発行事業者となりました。
岡部氏は「社会のジレンマを突破する」というミッションを掲げ、新しい金融インフラとしてJPYCの普及と革新に取り組んでいます。
JPYCの特徴とは?国内初円建てステーブルコインの強み
JPYCが持つ主な特徴をまとめると以下の通りです。
-
価格安定性:
常に1 JPYC=1円の価値を保つよう設計されており、日本円と連動した安定した価格を実現しています。JPYC株式会社が裏付けとなる日本円資産を保有し、ユーザーはJPYCを同額の日本円に償還できるため安心です。 -
裏付け資産による信頼性:
発行されたJPYCの価値は、日本円の預貯金および日本国債を裏付け資産として保全することで保証されています。この堅実な準備金により、JPYCの信用度と価格の安定性が支えられています。 -
高速・低コストの送金:
ブロックチェーン上で発行されるため、JPYCによる送金は銀行を介さず直接相手に即座に届けることができます。国内外問わず24時間365日リアルタイム送金が可能で、銀行送金に比べて手数料も格段に安く抑えられます。 -
マルチチェーン対応:
JPYC(現JPYC Prepaid)は現在Ethereum、Polygon、Gnosis、Arbitrum、Optimism、Avalancheなど複数のブロックチェーン上で発行されています。ユーザーは自分の用途や手数料の安さに応じて好きなチェーン上のJPYCを利用でき、ブロックチェーン間の選択肢が広い点も利点です。 -
多様な活用シーン:
JPYCはデジタル通貨として決済や送金、NFT購入、Web3サービスでの支払いなど幅広い用途で活用されています。価格変動が無いため、暗号資産では難しかった実用的なユースケース(例えば企業間決済や個人間少額送金)でも安心して利用できます。 -
法令順守と安全性:
JPYCは日本の法制度に則り発行されており、資金決済法上の「電子決済手段」に位置付けられる合法的なデジタルマネーです。暗号資産交換業のような不確実性ではなく、発行者による厳格なKYC(本人確認)や不正取引監視も行われており、安全に利用できる環境が整備されています。
JPYCの3つの種類と価格安定の仕組み
JPYCには現在「JPYC Prepaid」「JPYC(新型)」「JPYC Trust」という3つの形態があります。それぞれ利便性と法的性質が異なるため、自身の用途に合わせて使い分けることが重要です。
3種類のJPYC「JPYC Prepaid」「JPYC」「JPYC Trust」の違い
JPYC Prepaid(前払式支払手段としてのJPYC)
「JPYC Prepaid」は、2021年に初めて発行された従来型のJPYCを指します。
法的にはプリペイドカード等と同じ前払式支払手段として位置付けられており、発行元であるJPYC社に日本円を支払って購入するデジタルプリペイド券のような性質を持ちます。当時は現在のようなステーブルコインに関する明確な法整備が無かったため、この方式での発行が採られました。
JPYC Prepaidの大きな特徴は「発行体から円への直接換金ができない点」です。購入したJPYC Prepaidは、JPYC社の提供するサービス(JPYC Appsなど)でAmazonギフト券などのポイントや商品券に交換することができますが、JPYC社にJPYCを送り返して現金を払い戻すこと(償還)はできません。
そのため、JPYC Prepaidはあくまで「日本円と等価の価値を持つトークン」ではあるものの、法的には電子マネーではなく前払い式のデジタル商品券のような扱いでした。しかし、JPYC社が常に1 JPYC = 1円で販売・流通させることで実質的な価値維持が図られており、ユーザーはJPYC Prepaidを使って各種商品購入やサービス利用が可能でした。
なお、2025年5月30日でJPYC Prepaidの新規発行は終了していますが、発行済のトークンは引き続き利用することができます。
JPYC(資金移動業型のJPYC)
新しい「JPYC」は、2023年の法改正後に登場する資金移動業型の日本円ステーブルコインです。
JPYC社が2025年8月に資金移動業者として正式登録を受けたことで発行が認められた、日本初の電子決済手段(デジタルマネー)としてのステーブルコインになります。このJPYC(新型JPYC)は、1 JPYC = 1円での日本円への償還が保証されたデジタル通貨であり、法的にも銀行預金と同等に保護された仕組みと言えます。
資金移動業型のJPYC最大の特徴は「購入したJPYCを発行体に送って現金化(償還)できる点」です。ユーザーは所定の本人確認(KYC)手続きを経てJPYCを取得し、いつでも発行元に1 JPYCを1円で買い取ってもらうことができます。
これによりJPYCはほぼ現金と遜色ない安心感を持つデジタル円となり、利用規模の大幅な拡大が期待されています。なお、新型JPYCと旧JPYC Prepaidは別のトークンとして発行されるため、両者を直接交換することはできません。
JPYC社もJPYC PrepaidからJPYCへのスワップ対応は行わない方針を示しています。新型JPYCはまずイーサリアム、アバランチ(AVAX)、ポリゴン(POL)の3チェーンで発行開始予定であり、今後他のチェーンへも順次展開が検討されています。
JPYC Trust(信託型ステーブルコイン)
「JPYC Trust」は、信託銀行を活用した信託型の日本円ステーブルコインとして計画されているものです。
JPYC株式会社は2023年11月に三菱UFJ信託銀行およびそのデジタル資産プラットフォームProgmatと提携し、このProgmat Coin基盤上でJPYC Trustを発行する予定であることを発表しました。JPYC Trustでは、ユーザーから預かった日本円の裏付け資産を三菱UFJ信託銀行が信託という形で厳格に保全します。
JPYC Trustの特徴は「資産保管を信託銀行が行うことで発行主体の信用リスクを大幅に低減できる点」にあります。仮に発行企業に何かあっても、信託された資産は守られるためユーザーは安心です。信託型ステーブルコインはより堅牢な仕組みを持つことから、一度に扱う金額が大きい取引や企業間決済への利用を想定しているとされています。
1JPYC=1円の価値を維持する仕組み
JPYCが1円の価値を常に維持できるのは、発行体による裏付け資産の管理と需給バランスの調整によるものです。JPYC株式会社は発行するJPYCに対し、同等額の日本円資産(銀行預金や国債)を保有することで価値を裏付けています。
ユーザーがJPYCを日本円に戻したい場合は、発行体が1 JPYC=1円で償還に応じる仕組みになっており、市場価格が大きく乖離しないよう設計されています。この換金保証があることで、JPYCは常に銀行預金に近い安定性を持つデジタル通貨として機能します。
なお、JPYCは発行当初こそ法的理由から直接円に戻すことができませんでしたが、発行体が常に1円で販売し、さらに公式サイト上で1 JPYC = 1円として各種ギフト券等に交換できるサービスを提供することで、二次市場でも価格が1円から大きく乖離しないよう保たれてきました。
このように公式の利用機会を保証する工夫により、JPYCは安定した価値を維持しています。今後は新しいJPYC(後述)において法定通貨への直接償還が可能となり、さらに強固な価格安定性が実現する見込みです。
ステーブルコインとは
JPYCの購入方法(買い方)と取扱暗号資産取引所
JPYCを購入できるサービス・取引所
JPYCを入手する方法はいくつかあります。最も基本的なのは、JPYC株式会社の公式サービス「JPYC Apps」から直接購入する方法です。
JPYC公式サイトの案内に従って日本円を入金し、自身の暗号資産ウォレット宛にJPYCトークンを発行してもらうことで入手できます。発行体から直接購入するため、確実に1 JPYC = 1円のレートで手に入れられる利点があります。※2025年5月30日でJPYC Prepaidの新規発行は終了
2025年8月現在、JPYC Prepaid(旧JPYC)の国内暗号資産取引所での上場例はありませんが、秋に予定されている資金移動業型「JPYC(新)」の発行開始に合わせて国内取引所で売買できるようになる可能性があります。
なお、すでに発行されているJPYC Prepaidはイーサリアムやポリゴン等のブロックチェーン上のトークンでもあるため、SushiSwapなどの分散型取引所(DEX)を利用してユーザー同士が自由に売買できる環境も存在しています。
DEX(分散型取引所)とは
JPYC購入の手順と注意点
JPYCを安全に購入・利用するための一般的な手順と注意点を説明します。
-
対応ウォレットの準備:
JPYCを受け取るには、イーサリアムやポリゴンなどJPYC対応ブロックチェーン上で動作するウォレットアプリ(例:メタマスク等)が必要です。まず自分用のウォレットを作成し、秘密鍵や復元フレーズを厳重に管理してください。ウォレットのネットワーク設定でJPYCを発行したチェーン(イーサリアム、ポリゴン等)を選択できるようにしておく必要があります。 -
公式サービスで購入する場合:
JPYC公式サイト(JPYC Apps)に登録し、ガイドに沿って本人確認(KYC)を行います。その後、指定されたJPYC社の銀行口座に日本円を振り込みます。入金が確認されると、登録したウォレットアドレス宛に等価のJPYCトークンが発行されます。
例えば1万円を入金すれば、ネットワーク上のあなたのアドレスに10,000 JPYCが送付されます。初回は本人確認等で数日かかる場合がありますが、2回目以降は円入金からJPYC受取まで比較的スムーズに行えます。 - 暗号資産取引所で購入する場合(2025年8月時点では未対応):
-
DEXで交換する場合(JPYC Prepaidのみ可):
メタマスク等のウォレットに他の暗号資産(ETHやUSDTなど購入資金となるトークン)を用意し、対応するブロックチェーンネットワークに接続します。
SushiSwap等のDEXでJPYCのプールを選択し、スワップ(交換)トランザクションを実行します。交換後は自分のウォレットにJPYCが残高として追加されます。DEXではガス代(ネットワーク手数料)が発生する点に注意し、十分なETH等を用意しておく必要があります。
JPYC購入時にはいくつか留意すべき点があります。
まず、JPYCは対応チェーンごとにトークンが発行されていますので、送金先のチェーンを間違えることがないよう注意してください。例えば、ポリゴンチェーンのJPYCをイーサリアムアドレスへ直接送ると資金を失う恐れがあります。公式サービスで購入する場合は基本的に誤送信の心配はありませんが、自分でウォレット間送金する際はチェーンの選択に気をつけましょう。
また、JPYC Prepaidと新型JPYCは異なるトークンであるため、サービス利用時にどちらに対応しているか確認が必要です。新型JPYCであれば発行体による償還(現金化)が可能ですが、JPYC Prepaidしかまだ流通していない場合、それを現金化することはできません(ギフト券等への交換は可能)。2025年秋以降は新型JPYCの流通が本格化する見込みなので、移行期には混同しないよう注意してください。
最後に、安全のため公式・信頼できる窓口を利用することが大切です。JPYC人気に便乗した詐欺サイトや不正トークンの存在も考えられますので、公式サイトのURL(jpyc.jpやjpyc.co.jp)をよく確認し、SNS上の非公式な勧誘等には引っかからないようにしてください。
メタマスク:初心者向けにわかりやすく解説
JPYCの使い方・活用|日常決済や企業間決済まで
JPYCを使った決済の例
JPYCは法定通貨と価値が連動しているため、日常の様々な決済シーンで活用することができます。その代表的な例がNFTやWeb3サービスでの支払いです。
例えば、日本人クリエイターが発行するNFTを購入する際、これまではイーサリアムなど価格変動のある暗号資産で支払う必要があり、決済時と受取時で価値が変動してしまうリスクがありました。
JPYCで支払えば常に1円=1 JPYCなので、購入者も販売者も日本円建てで価値を認識でき、安心して取引できます。実際に国内のNFTマーケットプレイスではJPYC決済に対応する例も出始めており、安定した決済通貨として重宝されています。
また、JPYCは一般的なオンラインショッピングやサービス課金でも代替の決済手段となり得ます。JPYC社の提供する「JPYC Apps」では、JPYCを使ってAmazonギフト券や各種プリペイドカードを購入することができ、JPYCで間接的に様々な商品・サービスに支払いが可能です。これはJPYCを一度日本円に戻す手間なく、有価サービスに直接充当できる便利な使い方です。
今後、新型JPYCが普及すれば、加盟店での直接JPYC決済も現実味を帯びてきます。例えば飲食店やECサイトがJPYC受け取りに対応すれば、ユーザーはスマホウォレットから即時に支払いを完了でき、事業者側も円建てのデジタルマネーとしてそのまま受け取れるため、決済手数料の削減や送金スピード向上といったメリットがあります。
企業間取引においても、JPYCの利用が模索されています。特にJPYC Trustのような信託型ステーブルコインが実現すれば、額の大きいBtoB決済でもデジタル円での即時決済が可能となり、銀行営業日に縛られない資金決済が可能です。
実証実験の例として、2025年2月に日立製作所やJPYC社を含む複数企業が連携し、暗号資産・ステーブルコインを用いたAML(アンチマネーロンダリング)体制の検証を行うプロジェクトが発足しました。ここでも、安全・安心なデジタル決済インフラとしてJPYCの活用が期待されており、企業間決済への実装に向けた動きが進んでいます。
JPYCを使った送金の例
JPYCは個人間送金や国際送金の分野でも大きな利点を発揮します。従来、国内銀行間の送金には数百円程度の手数料と営業時間内での手続きという制約があり、国際送金に至っては数千円の手数料と着金まで数日を要するのが一般的でした。
JPYCを利用すれば、インターネット経由でウォレット間送金するだけなので、手数料はごくわずか(ネットワーク手数料のみ)で済み、送金スピードも数十秒~数分程度と高速です。例えば、友人や家族にお金を送りたいとき、相手のJPYCアドレス(ウォレットアドレス)さえ分かれば即座に資金移動が完了します。深夜でも週末でも関係なく送れるため、緊急の送金ニーズにも対応できます。
例えば海外在住の家族に仕送りをする場合、円をJPYCに替えて送金し、相手側はJPYCを現地通貨に交換します。銀行を使うよりはるかに安い手数料で済み、着金も即時です。
日本の大手金融機関もこのメリットに注目しており、2025年3月にはSBIホールディングスがステーブルコインを活用した低コスト海外送金サービスを開始すると報じられました。円建てステーブルコインであるJPYCの存在は、こうした国際送金サービスの基盤としても期待されています。
JPYCを使った送金は、資産運用の面でも有用です。JPYC社の岡部氏は「ステーブルコインによって海外にすぐ送金したり、自分で自分の財産を管理しつつ運用することができるようになる」と述べています。
JPYCで資金を保有すれば、値動きのある暗号資産に換えることなくDeFi(分散型金融)で運用したり、必要に応じて海外の取引所やサービスに送金して運用商品を購入するといった柔軟な資産移動が可能になります。要するに、JPYCはデジタル時代の現金同様の流動性を持っており、送金・受取・運用の選択肢を飛躍的に増やすツールとなり得るということです。
ステーブルコインは金融決済の未来
JPYCの将来性と今後の展望|国内利用拡大と海外展開の可能性
JPYCを取り巻く最新動向と今後の計画
JPYCを取り巻く環境は、2023年以降大きく前進しました。最大のトピックは、2025年8月にJPYC株式会社が資金決済法に基づく資金移動業者として金融庁に正式登録され、日本初の円建てステーブルコイン発行事業者となったことです。
この登録により、JPYC社は法律上初めて円と1:1で連動する電子決済手段(ステーブルコイン)を発行できる資格を得ました。これは日本のデジタル資産業界にとって画期的な出来事であり、JPYC社は「なるべく早く日本円ステーブルコインの発行を進める」と表明しています。
登録完了を受け、JPYC社は新たな発行・償還プラットフォーム「JPYC EX」を数週間以内(2025年秋)にも立ち上げる計画です。JPYC EXでは、ユーザーがオンラインで日本円をJPYCに交換・発行し、またJPYCを円に償還する一連の手続きを全てブロックチェーン上で完結できるようにします。
注目すべきは、その手数料体系で、JPYCの発行や償還・送金手数料は当面無料とする方針が打ち出されています。JPYC社は裏付け資産として保有する国債の利息収入を運営費用に充てることで手数料ゼロを実現し、ユーザーの負担なくJPYCを利用できるようにする計画です。これは利用者にとって大きなメリットであり、他の決済手段と比べたJPYCの競争力向上につながる可能性があります。
JPYCの今後の展望としては、まず国内外での利用拡大が挙げられます。JPYC社は国内の企業や地方自治体との協業を強化し、JPYCを活用した新たなユースケース開拓に努めるとしています。送金・決済インフラとしてJPYCを組み込みたい企業との提携や、JPYC決済対応サービスの拡充が期待できます。
また海外展開にも意欲を見せており、特にアジア地域で円建ての国際送金・決済手段としてJPYCを活用してもらうことを目指しています。
2025年8月には、日本のフィンテック企業シンプレクス株式会社がJPYC向けの取引システム提供を決定したとの発表もありました。このシステムではアカウント開設からウォレット管理、ステーブルコイン取引まで一括提供される予定で、JPYCを含むステーブルコインの普及を技術面から支える動きとされています。
一方で、市場競争の視点も見逃せません。世界のステーブルコイン市場(時価総額約2,500億ドル/約37兆円)では米ドル連動型のテザー(USDT)やUSDコイン(USDC)が圧倒的シェアを占めています。日本国内でも今後、海外大手発行体が円建てステーブルコイン市場に参入する可能性があります。実際、2025年3月にはUSDC)の発行元であるCircle(サークル社)が日本での提携先拡大を表明しており、日本市場への関心を示しました。
さらに国内のメガバンクや決済企業も、自社での円デジタルマネー発行を検討し始めています。こうした競争環境の中で、JPYCが日本発のステーブルコインとしてどのように差別化していくかが注目されています。JPYCはパブリックブロックチェーン上で広く流通していることや、民間スタートアップならではの俊敏性を強みとして、先行者メリットを活かしつつ市場優位を維持していく戦略とみられています。
JPYC社は成長目標として、今後3年間で発行残高1兆円規模を目指す方針を掲げています。長期的には10兆~100兆円規模の発行も視野に入れており、市場の需要拡大に応じて飛躍的な成長を狙っています。
ただし、現在のライセンスでは1日あたりの発行・償還額に上限(第二種資金移動業者として1日100万円までなど)があるため、JPYC社は将来的に第一種資金移動業者ライセンスの取得も視野に入れ、規制当局と協議を進める考えです。ライセンス区分を上げることでより大口の取引に対応できるようになり、企業や金融機関もJPYCを扱いやすくなります。
法整備の追い風もあり、JPYCは日本のデジタル経済における基盤通貨の一つとなる可能性を秘めています。今後も日本の法規制に完全準拠しつつブロックチェーン技術のメリットを最大限に活かし、JPYCは円建てステーブルコイン市場をリードして成長を続けていくとみられています。
万博ウォレット、USDC・JPYC対応へ
JPYCまとめ|JPYCが変える投資・決済の新時代
JPYCは、日本円と連動した価値を持つ国内初のステーブルコインとして誕生し、着実に存在感を高めてきました。
1 JPYC=1円という揺るぎない安定性と、ブロックチェーンならではの迅速・低コストな送金を両立することで、JPYCは個人から企業まで幅広いユーザーに新たな金融インフラの可能性を示しています。開発企業であるJPYC株式会社の挑戦と、2025年の法的承認取得によって、JPYCは単なる「暗号資産風のトークン」から正式なデジタル円へと進化を遂げました。
特徴・仕組みの面では、JPYC Prepaid(旧型)、JPYC(新型)、JPYC Trustという3形態を通じて利用シーンに応じた選択肢が提供されます。決済・送金の具体例からも分かる通り、JPYCは既に現実の経済活動に組み込まれ始めており、国際送金の効率化やNFTマーケットでの決済など、その実用性は日増しに高まっています。
今後の展望として、JPYCは日本国内のみならず国際的な決済ネットワークの一翼を担う可能性を持っています。規制当局の認可を得たことで信頼性は盤石となり、大規模な発行量の目標も掲げられています。
海外勢との競争や他社の参入といった課題はあるものの、日本発のステーブルコインとして培った知見と先行者メリットはJPYCの大きな強みです。JPYCが普及すれば、お金のやり取りの在り方が変わり、銀行振込や現金決済に代わる新しいデジタル円のエコシステムが形成されるものとみられています。
日常生活でも、JPYCを使って支払いをしたり、家族に送金したり、資産を運用したりすることが当たり前になる未来がすぐそこまで来ているのかもしれません。JPYCは「エン(円)をつなげる」ステーブルコインとして、これからの日本経済とWeb3社会を支える基盤になり得る可能性があります。
JPYC関連リンク
JPYC関連の注目記事はこちら
サムネイル:AIによる生成画像